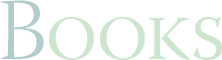
魅せられた溪谷あるき
野口冬人
年報1わらじ 巻頭言より
沢歩き、あるいは溪谷歩き、という登山のひとつの方法について、私は久しく興味を持っている。興味を持つだけでなく、その方法による山行をかなり強行に実行して来た。
実際、夏の暑いさなかに、重い荷物を背負って、汗まみれ、泥まみれになって、尾根の縦走をすることを考えると、溪谷に飛沫をあびて、わらじに清冽な谷水を受けながら、溪谷を溯る楽しみは、ひとたび経験すると、もう忘れることのできない魅力となってしまうのである。
とにかく溪谷歩きには、たいていの場合道がないのであるから、谷へ行ったらなにが出てくるかわからない。行手をとざす巨大な滝場もあれば、通過のできない深い淵や、切り立った両岸の岩壁がみごとにせばまった廊下など、次々に自然の変化をみせて、私たちの気持ちをいっときも緊張をときほぐすことがない。それだけに、いっぱいに張りつめた心の動きと、自然の作り出す妙味との対決が、ともすると私の心に、一本の芯を持ちこむかすがいともなるような思いをいだかせることもある。
道のない谷を行くときには、そのルートを自分自身の判断によって定めなければならない。それだけに、未知の谷へ入った場合の、地形やルートの判断にそそぐ神経のこまかさも大変なものである。たびたび紹介されている一般的な谷については、それほどの心配もないが、文献のない谷へ入った場合の神経の消耗は大変なものがある。いっときも緊張をゆるめることができない。
だがまた一面においては、溪谷に入るよろこびや楽しみは、そういった未知のものに対する、私たちの気持の動きが、緊張を強いられれば、強いられるほど大きなものであるといえるものであろう。
人の心のうちには、未知を求める気持は誰でも持っている。それを満足させてくれるものに谷歩きという山登りのひとつの方法が、あたかも当てはまるものなのである。そしてまたそこに極度の緊張を強いられるということは、とくに若い人の心に、魅力を覚えさせるひとつの要員ともなっている。それがあるいは個々において、しっかりとした自覚にもとづかないものであっても、それは現代の若人の心にうったえかける、多くの要素を溪谷歩きの中に見い出されるものである。谷歩きが若い人のあいだに絶対的な人気があるのは、こうしたことからみてもうなづかれるものである。
丹沢山塊が、京浜間の若人の間に絶対的な人気を保って、シーズンの休日には列をなして登山者がおしかけるのも、ひとつにはその山塊のコースの大部分が沢歩きのルートによって占められているからにほかならない。それはたしかに交通の便のよい、東京から近い位置にあるというだけの理由だけでなく、若い人たちを絶対的に惹きつける要素である谷歩き、沢歩きのメッカであることが、東京周辺で最大の登山者を訪れさせているもととなっているのである。
私はひところ沢歩きにこりだしてから、丹沢へは随分通ったものである。私は一時期においては、丹沢と三ツ峠と谷川岳の三ケ所をめぐって、他はまったくといっていいほど行かなかったことがあった。そのころは十代の終わりから二十代に足を入れるあたりであって、私は沢歩きと岩登りでなければ、山へ行ったという気がしないとまで思い込んでいったものである。いま考えてみるとまことに不思議な気がするものであるが、私は別にそれを後悔していない。青春の一時期における、私自身にとっての、いわば人生の旅路のうちのひとつの記録でもあるわけだ。
思索の幼かったころにおける未熟な考えによって行動され、記録されて来たことがらは年輪を重ねることによって、次第にその考え方において多くの矛盾を生みだしてくる。しかしながらそれは成長の過程における段階のひとつひとつの踏跡であるから、それぞれにおいても異にするのは当然であり、仕方がないことである。それは私自身においても、私の山旅における思索の歴史でもあり、小さな思想の積み重ねにおいて、そうした過程のなかからひとつのイデオロギーが求められて行くのである。
丹沢山塊にいく本の沢のルートがとれるのか、私は詳しく数えてみたことはないが、私はこれはと思う沢には入ってみた。若い仲間はそんなことをいっても私が近ごろ半島や岬めぐりばかりしているものだから信用しなかったが、あるとき西丹沢や神ノ川の方へ入る若者に、沢の様子をことこまかに説明して行かせたところ、アプローチはかわっても滝場の様子などはほとんどかわってなく、スムースに山行ができて、それからすっかり信用するようになったというお笑い草もあった。それはともかくとして丹沢山塊は一見単純そうな山であるが、反面では実に複雑な山塊である。ガレは常に押し出して、沢の様子をたえず変えてしまう。
十年くらい前のことであるが、当時の西丹沢への通い道であった雨山峠越えのコースの寄沢の河原に大きなエンテイが工事されたことがあった。私は2〜3週間続けてここを歩いたが、なんと前の日曜日に完成したエンテイが、次の週だったかその次の日曜にはもう完全に埋まって、広い河原を作り上げていたことがあった。正に丹沢は生きている、と私は思った。
ひところ那須だとか、南会津、越後方面に多く出かけるようになって数年ばかり丹沢山塊から足を遠のかせていたが、一昨年あたりから今年にかけて再び丹沢の主なところをひと通り歩きなおした。昨年の7月に水無川の本谷を遡行したところ、主な滝場(丹沢では棚といっている)にクサリや針金がつけられてあったのには驚いたし、いく人もの墜死者を出している大棚の左手の壁は無惨にも崩れてしまっていたのにひとかたならず驚いた。
しかしそうした反面、西丹沢の小川谷廊下などは、昔と変わることなく磨かれた沢床に深い釜をみせ、豊富な水量を流下させ、十数年前に遡行したときと同じように腰まで入る深い徒渉をさせられたりして、丹沢の黒部の味に思いを新たにした。
とりとめのない文章をだらだらとしるして来てしまったが、私は山登りのひとつの方法として、溪谷からの山旅をかなり前から提唱している。それは私たちのわらじの仲間という小さな山の会を結成したときからはっきりとうたい出したものであるが、その根本の考えにあるものはパイオニアワークにあった。未知、未開の山を探るには溪谷筋からルートをとることによって、きわめて容易に山頂に達しうるという考えにもとづき、またルートのはっきりしない山塊に新しいコースを求める場合、溪谷を行くことによって、そこには新鮮なものがいつも得られたのである。そしてなによりも自分自身の持てる力を精一杯そこにぶつけることが、未知の谷を行くことによってできたのもであった。
谷からの山旅はとくに新しいものではない。それは昔から行われていた日本古来の山登りのひとつの方法でもあった。だからそれをこと新しいあり方のようにうんぬんするのは少々おこがましいことかもしれない。だが、そうした古い方法は、アルピニズムの隆盛する現代においては、いつか顧みられなくなっていた感があった。私たちはそうしたなかにあって、単にわらじを履いた古い日本的な登山の方法に郷愁を感じるというだけにとどまらず、そうした中からひとつの新しいあり方を求めたいと考えた。
ほとんど開発されすぎとまでいわれるこの国においては、すでに未開の山、あるは秘境の地といわれるところはないといっても過言ではないかもしれない。だがそうはいっても、よく調査してみたらいまだに記録されないところは溪谷において、実に数多く見い出さたものであった。たとえば二十年、三十年前の記録はあっても、近年においては訪谷した人もないという深い谷はいくつも見い出された。南会津にしても、越後にしても、あるいは東地の背稜に喰い込む深い溪谷や、奥美濃の未開の谷など、私たちの心を魅了して止まない未踏の谷だには実に数多くあったのである。