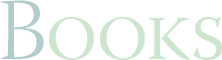
若林岩雄
年報4わらじ 巻頭言より
年間の活動報告としての「年報」という形式に変えてから、二冊目の年報である。従来の年報1、2は地域研究の成果報告として位置づけられていた。この年報は、言葉通り、年度報告である。昨年は「年報3」と謳うのに少し気が引けたが、どうやら定着しそうな気配になってきたので、この年報ではなしくずし的にではあるが「年報4」と名づけることにした。年報1、2を編集された先輩諸兄にはいろいろとご意見があろうかと思うが、ご了解願いたい。
H社の「日本登山大系」は一つのエポックメーキングになるような気がする。どのような経緯を経てこの企画が具体化されたか解らないが、「本邦初のバリエーションルート・ガイドの集大成」と銘打たれ、それなりの売れ行きを示し、かつそのキャッチフレーズに疑義をはさむ者が少ないとしたら、その背景として、(1)バリエーションルートは一通り出揃った。、(2)ある山域のバリエーションルートををトレースしたとする集団、ないしは個人が存在している、(3)バリエーションルートを主観の領域から客観の領域(ガイド集)へと移行させるニーズが生じてきた、という認識が一般化したということがあるさまに思う。いわば空白の領域はなくなったということである。また、編集方針自体も当初のラフなスケッチ程度のルート紹介が、刊を追う毎に覇権主義・ガイド主義に変わっている。もちろん、このシリーズによって空白の部分が逆に明らかになる、という言い方もできるが、しかし、一つの楽しみではあるにしても輪郭を縁どられた空白は、既に空白ではない。例え誰が残そうとしても、レールが敷かれた以上終点まで行く他はない。ぬりつぶされるのは時間の問題である。
私がもし“わらじ”の会員でなかったとしたら両手を挙げてこのシリーズを歓迎しただろう。これで情報が一部の山岳会の占有から解放される。数あるメニューの中から自分の好み、技量に応じてルートを選択することができる。権威ある登山家が示してくれた指南書なんだから疑うことはしない。この一冊を脇に携えて、私は、私にとっての未知・空白を一つ一つ私自身のものとすることができる。エキスパートにとって既知であったとしても、私自身にとっての見地の経験はいくらでも求めていくことができる。その手がかりができたというように、この大系を歓迎するだろう。
ところが、残念ながら私はパイオニアワークを標榜する“わらじの仲間”に所属している。私に個性があるように、会に個性があっても不自然なことではない。日本の労働市場が閉鎖的であるのと同様、山岳会組織にも閉鎖的な側面がありそうなので、個性がプラスではなくマイナスに作用してしまう懸念はあるが、会の個性は尊重されて良いと思う。その“わらじ”の個性は、未知を既知化するところに発揮されてきた。曰く「地味な山域を地道に登り続ける地に足がついた会」というような形容はそういうことであろう。ところが山岳会の会報や、雑誌の記録速報蘭に細々と沢の記録が掲載されている間は、未知はもっともらしく未知であった。少なくとも、沢の概念や、周辺領域の様子をつかむためさえにも、会報集めやら、図書館通い(私には本を買う財力がないので)やら、一定の作業を必要とした。しかし、今やガイド集一冊で全てがことたりるわけである。さらに、改訂版が発行さて続けるようになるとまさに完璧である。つまり、会の基本的な方針が危機に瀕することになる。「そんな事知ったこっちゃないや。私は好きな所へ行く」と言えないのが立場上辛いところだが、逆にそう言えないところに面白みもある。「登山の多様性」と単純に割り切れないのである。
今考えられる方法は幾つかある。一つは日本に見切りをつけ海外の沢を想定することである。要するに空白の域的拡大である。一つは冬の沢登りである。時期的拡大。一つは、岩登りの歴史を開拓期(その頂点がエベレスト登頂)→人工登攀期(ヒマラヤ鉄の時代として継続中)→フリークライミング期(興隆期)と独断的に時期区分し、この区分をアナロジーして、これから沢登りは人工登攀期+フリークライミング期を迎えるという考え方。いわば水線直登限界追求主義。茶化すような言い方になって申し訳ないが、溪谷登攀主義。一つは、沢登り+ONE主義。写真、釣り、山菜、泳ぎ、etc。一つは、山の中をクマ、カモシカ以上に自由に歩き回ろうという山中漂泊主義。自然融和型。一つは、徹底開拓主義。例えば、200m以上の側壁があったら全て登ろうというさまなもの。一つは、ツッパリはやめた、楽しければいいじゃないかという、山遊主義。この中で、どれという心算はないが、私自身は、意識的に可能な限り水線に忠実にトレースし、更に山行に+ONE(山菜、岩魚。しかし岩魚は眺めるだけに自己規制)を持ち込み、その上で、継続遡下行という様な山の面的な楽しみを追い求めたいと考えている。そして、氷瀑だけではない冬の沢歩きというような実験的な山行に対しては、少なくとも足を引っ張る事はすまいと念じている。
このような事情は、当然にこの年報の編集方針にも波及する。従来の年報は、いわば「登山大系」の「わらじ版」であった。逆にいえば、各々の山岳会の蓄積の総集編が「大系」ということにもなる。とすれば、従来のような「記録の集約」としての年報はそれほど面白味を持ち得なくなる。新しい年報方式を始めるにあたって、その性格を巡り、(1)記録(発表価値のある?)中心、(2)会山行報告を全て網羅する、(3)紀行、随想等個人的な経験談中心、のどれにするか迷ったが、結局、年報3、4は(1)の考え方を捨て、(2)の方針を原則とし、(3)の性格を持った報告が投稿されることを願ってきた。今後は他聞、(3)の性格がより強められることになろう。沢、岩、冬の縦走・沢、氷壁等オールラウンドな技術を自己のものとし、その上で自分の好みの山行(沢登り)を追い求め、その報告が年報に結実すれば素晴らしいと思う。
今回の年報は、原稿を寄せてくれた人は原則として全て掲載した。しかし、遡行図を依頼した人の何人かには出してもらえなかった。ルート図集に載っているような遡行図を書いても仕方がないという至極もっともな理由だ。また、遡行図を害悪視し全くの概念図しか書いてくれない人もいる。逆に「沢登りの楽しさは、その流れに沿って展開される、岩質の違いや樹相の変化からかもし出される雰囲気の変化の妙味であり、絶妙な高巻きルートや、ゴルジュ内のたった一坪程の砂地のビバークサイトの発見だろう。いつしか、参考図ではない、見ただけで遊び心をそそられる、『宝島』の地図のように、もろもろを盛り込んだ遡行図を書きたいと思う」(中野氏、年報2あとがき)という観点からの遡行図を寄せてくれた人もある。私のように文章を書くのがめんどうなので図に全部書き込んでしまうというタイプもある。どれがいいかは私には全く解らない。解答は、この年報が何年か継続されれば、この年報の性格も含めて自ずと明らかになってくるのではないかと思う。