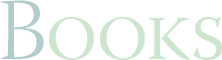
若林岩雄
年報5わらじ 巻頭言より
地味・地道をモットーとし、人影稀な山域にフィールドを見出してきた当会にも新しい波は着実に押し寄せ、その波形を次第に鮮明にさせているようだ。この年報に収録された1981年度の山行の範囲内でそれらの動きはまだ萌芽でしかないが、82年に入ってからの山行では幾つかの動きが明瞭な輪郭を縁どり始めている。
ひとつはハード・フリー志向の浸透・定着であり、ひとつは冬の沢登りへの試みであり、ひとつは個人レベルでの地域研究見直しシリーズの開始である。これらの動きは言葉をかえれば、ハード・フリーには登攀方法のみならず山との係わり方の発送転換があり、冬の沢登りは登山のフィールドの恐る恐るの拡大であり、地域研究見直しシリーズも従来の沢登りに質的転換をもたらす要素をはらんでいる。つまり、山登りの視点と対象と方法のそれぞれにおいて質的な変化がもたらされれいるともいえよう。
山登りの世界も他と同様、一つの壁に直面して初めて革新的な発想・対象・方法が芽生えてくる。いわば「量的変化から質的変化への移行」というような弁証法の法則に従っているともいえるが、比喩的に言うと、衝立岩が一般化したと認められた時点でハード・フリーの素地が醸成され、沢のルート図集が出揃った時点で従来と異なった沢登りの方法が市民権を得るようになっている。当会の場合は、このような世間一般の動きとは三歩位距離をおいた頑固さにレーゾンデートルを見出してきたのであるが、その存立基盤が堀りくずされつつある以上そう安穏としてもいられないだろう。さて、前記したような三つの事情はどんな波及をもたらすのであろうか。結論は五里霧中ということにないかねないが、とにかく始めてみよう。
当会の組織規範は我流の解釈で恐縮だが、比較未知な山域の「地域研究」を、特殊日本的な登山スタイルである「沢登り」という方法を用いて「会員全員」が参加するという点にあった。目的意識は極めて鮮明であり、かつ理想的なものであった。個人的嗜好よりは会の方針が、面白そうな事にヮッと飛びつくよりは地道な活動が、岩登りよりは当然沢登りが、個人的技倆よりはパーティシップがそれぞれ優位におかれてきた。ところが現在の会の事情は幾つかの局面でこのような価値基準をゆり動かしているようにみえる。具体的にいうと、一つは個人(各会員レベル)の志向性の分化に帰困する山行(会レベル)の多様化であり、その典型として82年度の冬合宿は縦走と沢の二形態、春合宿はスキーと縦走と沢と古典的な壁登りとハード・フリー的岩登りという5形態にもわたる合宿の分散化がある。第二は志向の相違の結果として会員間の技術レベルの乖離及びパートナーの固定化と会の枠を超えたパーティ編成の問題がある。そして第三は、以上の結果として表面的ではあるが会のまとまりの欠如という形で現われている。このような動きに対する評価も従って二様であり、ある人にとっては多様な志向性を許容することによって各々の個人の志向を自己実現しうる好ましい動きとして映っているのに対し、他の人にとっては会の組織力の衰退あるいは会に分裂をもたらす好ましからざる動きとして把えられていよう。
平日の夜T公園へ行けば、薄暗い灯りの中で薄汚れたハード・フリーヤーに混って一層薄汚れた出で立ちの当会の何人かが、ヤモリの様に石垣にはりついている。その中に時としてYシャツとズポンの裾をまくり上げた冴えないオジンも混り合っているが、その御尽はふだん代表などといばっていてもこの場では頓とだらしない。似た様な境遇の私も幸なことに「登れないより登れた方が楽しい」という単純な価値感の持主だから、ハード・フリー派を賛嘆しこそすれ拒否する理由は何もない。勿論「石坦で7級を登れても蒙雪のラッセルはできないだろう」なんていうことは意識の埒外である。私にとって少しでもプラスがあればそれらは全て教師となる。
ところで最近、ハード・フリーの実践者達の生活と意見といった様なものが出回り始めたが、それらを読んでみると私の発想との違いがなんとなく見えるようになってきた。一つは「ハード・フリーは登山ではなくスポーツだ」という点である。確かにハード・フリーヤーにとって対象が山の中にあるか否かは問題ではなく、固くかつ快適な岩があれば場所は問わない。アプローチも短いほど良く、車で取付に至ればなお良い。私達が腰まで水に浸って本流を溯り、ようやく取り付いたのが垂直でボロボロの泥ルンゼだというのとは大違いである。
二つめは用具に対する視点の相違である。ハード・フリーの用具は一つ一つが単能化し道具の専門化が著しい。EB然りナッツ然りフレンズ然り、ついでにチョークなんてのもある。私は逆に一つの道具でなるべく多くの状況にまに合すことを考えている。一つの道具の多機能化であり、応用範由の広い道具の選択である。今後もハード・フリーヤーにとっては極論すれば広いクラックにはそれ用の、狭いクラックにはそれ用の道具をという形で発想されるだろう。根っ子のところは自然に対し人工的な部分を回避しょうという点で同じであっても、一方はそれを更に高次の道具で解決しょうとしているのに対し、他方は技能で解決したいと考えている、という様な違いがあるのかもしれない。
第三は山を見る日の相違がある。先にも云ったようにハード・フリーヤーにとって対象が山である必要はなく一つの興味あるポイントであればよい。自然から様々な爽雑物を排除した純粋な岩壁に近づけば近づくほどよいことになる。対して私にとっては山はあくまでも総体としての山でなければならず、空気も風景もまず山の中の「もの」でなければならない。そして山との係わりをより拡く楽しくするために、つまり山に対する「自由度」を拡げるために方法があり、その時々の状況に応じて様々の方法の中から適合するものを選択していく。従って方法はなるべく多種のものを身につけたいと考えており、その一つとしてハード・フリーによる登攀技術が位置づけられる。山には四季があり、そして悪天と好天がある。山には沢があり岩があり薮がある。それらは全て私の対象である。特に私の場合は、山屋は自然の全状況に対応できなければ山屋ではない、登山道のある縦走を何年つづけようと山のベテランとはいぇない、山岳会に何年在籍しようとリーダーの後ろについていくだけでは山の経験年数はゼロだ、といぅ偏執的な強迫観念があるので余計そう思ってしまうのだろう。
つまるところ、ハード・フリーヤーを現代テクノロジーの最先端を走るイノベーターとすれば、私達はそれらにより開発された技術の中から自分達に利用できるものを取捨選択し、その応用を考えるアーリーアダプターということになろうか。あるいは専門家集団とマルチ人間・複合的ナンデモ屋集団とでもいった方がいいだろうか。いずれにしてもハード・フリーからは登り方、用具、トレーニング方法等の面で学ぶべき点が多い。従来の登攀方法が「三点支持+根性」、トレーニング方法も「走れ走れ+根性」といった徒弟制度的養成法であったのと比べると技術労働者養成カリキュラムが整備されつつあるという感じに近く、今後沢登りを続ける上においても登肇技術というより「登る動作を説明する用語」はハード・フリーから学ぶことになる事は疑問の余地がないように思える。もう少し具体的にいうと、レイ・バックとかオポジション、ジャミンクという動作は昔からあったが、その動作を表現し説明する用語がなかった。しかしハード・フリーによってそれらの動作の一つ一つに表現が与えられ、それにより初めて登る動作が言葉で分解され伝達可能となり主観の領域から客観の領域のものとなっている。ただ残念なことに輸入品の常、ほとんど全てがカタカナで表現されているので私の様なカタカナ音痴には意味するところを理解するのに大分時間がかかってしまうという難点はある。そしてついでに私自身の好みをいうと、登山がスポーツのみに限定されるなら私は多分サッカーやラグビーを趣味として選ぶだろう。
冬の沢登りはアイス・クライミングのフィールドの代替としての冬の沢という意味では現在大流行中である。氷壁専用の道具が開発されたこと、それにそういう道具を持てば使ってみたいと考えるのは人間の常だ。しかし氷壁登攀というのはかなり前から行なわれていたし、当会でも設立当初から奥多摩や西丹沢、奥秩父での山行が組まれていた。1975年には当会の小林さんが甲斐駒の奥駒津沢をオールフリーで登ったなんてのもある。ところでここでいう冬の沢登りというのは氷瀑とは関係なく、夏の沢と同じ様に冬の沢を遡行するという、考えただけで身の毛がよだつあの冬の沢登りである。溝江氏の独創によってつくり出された全く新しいフィールドである。これは対象となるエリアという点でも、装備の面でも現在熟慮検討中あるいは実験中という段階だろう。とても「全員参加」で取り組めるという種類のものではない。しかし考えてみれば、山の遊び方という点では初めて純国産で開発された画期的な分野だろう。また、ヒマラヤ、アルプス、アンデス等のトレーニング的あるいは代替的位置づけではなく、日本の山それ自体に課題を見出した初めての形態であるかもしれない。従って装備も従来の登山の概念とは全く違った形で発想されている。今後どの程度の展開をみるか予想はつかないが、多分現在もっとも創造的な分野であることは確かだ。
地域研究見直しシリーズというのは月報316号で一応触れたが、単純明瞭、登り残した所は全て覗いてみようということで、まじめな言い方をすれば、ピークに至る過程としてのみの沢登りではなく、沢登りの楽しさの最も大きな要素「自然の変化の妙」を純粋に取り出してみようということになる。自然の諸相を凝縮している沢という一つの空間に可能な限り素直に接してみようということでもある。あるいはフリー・クライミングを岩登りの楽しさを純化したものとするなら、地域研究見直しシリーズは沢登りの楽しさ(その内実は全く逆であるが)を純化していこうとする方向かもしれない。その純化とは自然をあるがままのものとして受け入れ自然の摂理に即応した技術(むしろ技能)を自己のものとしていくことである。
以上三つの動きをつらつら考えながら今後の会の方向という様なものを考えてみるとかなりシビアな雰囲気になってくる。基本的な点は、今後の活動は組織依存ではなく個人主導にならざるをえないということである。高度成長期のように目的が外生的に与えられかつ単純明快であれば(社会的に認知された処女岩壁や未開山域の開拓のように)組織をあげて取り組むというような形も可能であろう。しかし現在はそのような条件は多分ない。大仰な言い方をすれば独創の時代、質の時代、課題は自らが探しそして解決していくべき時代なんていう云い方になるだろう。組織自体からは独創は生れない。担うのは個人である。組織はそれを加速することもあるし阻害することもある。個人を相互に刺激しあいながらより豊かな山行を組み立てることもできればそうでない場合もある。私自身の理想を云えば、沢という自由な空間を足場にして山と主体的に係わりあうことができる自立した個人の集合体といったような組織を夢想している。これが夢想に終り組織の形骸化のみを結果するか、具体的な形をとることができるか予測だにつかないが、まずは自分が今考えている山とのつき合い方を一つ一つ具体化していく事から始めてみたい。たてまえと先入見を少し隈の方へ置いておいて。