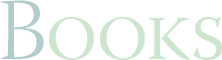
宮内幸男
年報16わらじ 巻頭言より
「わらじの仲間」はかわろうとしている。たぶんもうかわっているのだろう。
中高年登山者の急増、アウトドアライフの流行、脚光を浴びてきた沢登り、そんな社会情勢のなかで、たぶんそれらの反映としての会員数の増加、そして登山志向の差異化といった大きな流れが私たちをつつんでいる。
過去の活動にはいくつかの柱といったものがあった。理念としてのバイオニアワークであり地域研究であり、その実存形態としての内外から揶揄的に批判されてきた組織的登山である。さらに登山のジャンルとしての「沢登り」(“渓谷から頂きへ”)を加えてもいいだろう。
過去の活動はそれらの合成体としてあった。だが、これは自己批判的にいうのだが、各々が自立していたわけではなく、むしろ相互補完的な関係にあった。互いに支え合って初めて成立していた、と言っていいだろう。個人的にみればみんな色々な点で無理もしていたが、それだけの価値もあったということでもあるのだが。私の乱暴な考えでは、面白さ、快適さ、あるいは登攀性を、私たちは何のてらいもなく求めるようになってきた。当然そのなかで組織的登山の面白さは大きく後退していき、さらにその面白さを裏打ちしていた、パイオニアワークや地域研究の対象の喪失という現実がそれに追い打ちをかけた。そうしていま生き残っているのは、キャッチフレーズとしての「沢登り」だけなのだが、これもまたその目標が、快適さ、未知性、登攀性、その他(岩登り、オールラウンド、海外登山など)へと急速に分化しつつある、そういう状況にあるのだと思う。
山登りの面白さは色々とあるが、自然のなかでの肉体的な活動という当然の前提のほかに、未知性や登攀性の追求、仲間との体験の共有といったところにその核心があると私は思う。そういう三拍子そろった会心の山行を実現したくて、いっとき「一定水準以上の山行を会活動の基軸にすえる」「リーダー会主導で求心的な山行を実現する」てな方針を打ち出してみたが、それはかけ声倒れに終わった。
その理由は幾つもあるのだが、ここでは、組織の肥大化と会員の志向の差異の拡大、あるいは山にかける思い入れや情熱の相違といったところに求めたい。端的にいって、冬の剱岳に魅かれる仲間と雪山には行かない会員が、あるいは年間山行100日に達しようという仲間と合宿だけでいいから参加したいという会員が、ともに同じように活動していくのは、やはり難しい。
では、いわば解党的行為が必要なのかというと、決してそうではないだろう。私たちはたぶん、色々な相違を持ちつつも(当然だ)、仲間としての意義をもちそれを大切にしたいと思っているし、運営上面倒なことはあっても各人の活動をすすめていくうえで大きな障害は生じていないだろうし、それどころか互いの存在自体が有益であることを体験的に知っているからだ。人はいつでもゆっくり歩いているわけではない。逆に常に走りつづけているわけでもない。幾つもの選択肢が用意されているとすれば、その分自由度も広がろうというものだ。
かつて若林岩雄“名”代表は、「わらじの仲間は八ヶ岳型」てなことをいっていた。死んだ鈴木雅士は「わらじ派閥論」をとなえていた。私としては、「わらじの仲間」はいまや、いくつかのいわば“専門部会”の集合体なんである、といいきってしまいたい。約束事は面倒だし、高度な質の共同性もうっとうしい。だいたい俺は淡白なんだ。
それはともかく、“専門部会”というのは、独立していながら流動的というのが理想だ。とくにメンバーの固定化はなんとしても避けたい。あくまでも、いっでも交流可能な開かれた存在であってほしい。そして、それぞれの“部会”のなかに“リーダー会”があって、あるいはメンバーひとりひとりが運営主体としての自覚をもって、活動すればいい。そのうえで、別の“運営委員会”とでもいうべき組織が、全体的な活動を統轄すればいいんじゃないだろうか。そうすれば、古い考えやへんな負担感から解放され、個人としても組織としても、より自由に全面展開できるんじゃないだろうか。ただ、そのための大前提がある。会員ひとりひとりが、それぞれ独立した登山者でありたいということだ。ある者は自立した縦走者であり、自立した遡行者であり、自立した登攀者であるだろう。そのときはじめて、本気で遊ぶに値する充足的な登山が実現できるのだろうと思う。