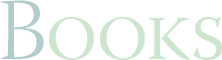
はじめに
宮内幸男
年報21わらじ 巻頭言より
冬を目前にした11月のなかば、もう沢登りでもあるまいと温泉でのんびりしようと考えた。会津の某温泉に宿泊と決め、ついでに近くの大戸岳に登ることにした。
登山口の立派な看板と駐車された8台の車にまずは驚く。私がこの山を知ったのは1978年(S53年〉刊行の「静かなる山」(川崎精雄他著)によるのだが、以後私の頭の中ではその姿のまま停滞していた。昨今の中高年登山ブームの最中にあってこんな盛況をみることになろうとは著者達も予想もしなかったことだろう。
登山道はよく整備されていた。平静は生の自然をもとめていながら、家人と一緒の今回などは薮こぎは困る。なんとも勝手なものである。この夏、東北は焼石岳できいた地元岳人の言葉を思い出す。登山者の増加に伴い色々な人がくる。同時に登山道への苦情も多く寄せられ、地元山岳会に整備の要請がくる。若年会員はおらず居てもみむきもせず、老会員がひとり汗を流していると。山域によって登山道の整備状況が異なるのはかつてなら当然のことであったが、今では均一な状態が求められる。ここでも同じようなことが起こっているのだろうか。
早くも登頂をおえて下山してくる人がいる。各々が声をかけていく。埼玉から来たという単独の男性からは“先週も登ってたでしょう”と唐突に問われて面喰らう。むろん面識はない。自分が毎週出かけているから当方も当然同様であるとみたのだろう。この思い込みは立派なものである。それとも、当方がよほどのヒマ人にみえたということか。だとしたらこれもまた素晴しい洞察力である。
新潟から来たという夫婦に会う。当方は東京からと応じれば、今回幾つの山に登る予定か、と問われる。遠方から来てまさかこの山だけではないだろう、というわけだ。この人達もまた、先週は鏡山に登って新雪の飯豊をながめてきた。といい、その前は高陽山に登った、という(こういわれてすぐに判る人もそう多くはないのではないか。むろん私はわかったけれども)。
折からの雨で滑べる岩稜を注意深く辿れば山頂に出る。霧雨の中、山形から来たという5人組が昼食を広げている。この方々もまた、地元や地方の山々に足繁く通っていることが、話の端々にうかがわれる。私たちもコンロを出して鍋物をあたためる。
女性3人組がやってくる。茨城からという彼女らに問われるままに今宵は温泉泊りとこたえれば、明日はどこに登るのかと声がかかる。セヶ岳、博士山、荒海山……、お気に入りらしい山々が次々と口にのぼる。大内宿をみて帰るというと、ならば小野岳だけでも行ってくればいい、小さな山だからわけはない、という。山に登らないなどは彼女らにとって全く想像の範囲外なのだ。
深田百名山ブームが云々されるいま、お仕着せ山好きだとか山の不勉強だとかが取り沙汰されているようだが、少なくともここにはそんな雰囲気は微塵もなかった。彼らは、地方のいわゆる渋い山を巡る特殊な人達なのかもしれないが、もしかしたら百名山を契機に山のひろがりや深さを知った人達であるかもしれない。みないい年をして次週はあの山へと目を輝かせている。眩しくみえたのは晩秋の斜光線のせいばかりではないだろう。
いつの間にか雪が遠のき、透けた光が満ちてきた。眼下には猪苗代の湖面が思いのほか高い。もう新雪をいただくはずの飯豊はあらわれず、その姿を妻に示すことはできなかった。
陽光を背にコーヒーのぬくもりを手にしているとこんな山もいいな、と思う。こういう感慨は、あえて拒否してききた成熟と呼ぶべきか、それとも老化の兆しなのか。ボッカ訓練や冬山の偵察以外に整備された登山道を辿るという山あるきをしなくなっていつの間にか20年にもなる。バリエーション偏重などというほどのことでもないが、いびつな山登りであるというべきか。わからないけれども、いずれと決めつける必要も、いずれがより大切と格付けする必要もないだろう。多様な登り方があり、多様な自然を巡る数多の関わり方がある。
温泉の付録で選択してよい山ではなかったな、と思いながら、宗教登山の名残りのあるという小荒岐沢を気にしつつ、午後の日差しにもう乾いた音をたてる黄葉を踏んで、ブナの森を下っていった。