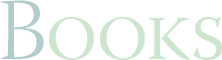
これからの「わらじの仲間」に向けて
早春の鹿島槍に逝った二人に思いを寄せて
チーフり−ダー 吉原清人
年報26わらじ 巻頭言より
『山岳会とは…』、今年の渓、そしてわらじの仲間の会員との山行では、常にこの疑問が隣りにいた。
チーフリーダーという立場にありながら、ここ数年「わらじの仲間」に魅力を感じなくなってきていた。この感覚が何時の頃から始まったのかは定かではないが、チーフリーダーを受けることが決まった頃から始まったのかも知れない。ちょうどその頃から、岩登りが高じてフリークライミングに力を入れるようになり、わらじにとって当然の事ながら沢登り中心の会の他のメンバーとの間に溝が出来つつあった。また、自分自身が他の人間に思いを巡らすことが出来ない未熟さから、快く山行を共にしてもらえる会員が減っていったためであろう。
大学入学後の勧誘でいくつかのサークルをまわった末、自分の居場所を見つけることができず、外の世界(=社会人の世界)に飛び出した。その後、都内のいくつかの山岳会を渡り歩き、89年に「わらじ」に何の気負いもなく入会した。当時のわらじは、沢の世界では名実とも第一線級のレベルだったらしく、飯豊川本流などでNHKなどの取材を受けていた。しかし、私自身は、そんなこととは全く知らず、単に「大学と家」の間にあるひとつの山岳会に過ぎなかつた。
当時、まだ山に足を踏み入れたばっかりの足取りも危なげなひよっこ登山者である自分が、大学のサークルや、社会人山岳会に求めていたものが何であったかはハツキリ覚えていないが、恐らく明確な考えはなかったであろう。ただ、サークルで言えば(昔はどではないだろうが)入学年度だけで決まる上下関係や山行スタイルを受け入れることは出来なかったし、外の世界では現役でない会員が会の中で強い影響力を持っていることに我慢が出来なかった。その結果としてサークルや山岳会に定着することができず、無積雪期は専ら単独の縦走、積雪期はゲレンデスキーをしていた。「安全な登山を目指すため」とか「より高い技術を身につけるため」、「よりレベルの高い山に行くため」などという、一般的な考えは恐らく持っていなかったであろう。
初めて行った大きな山行は、元代表の若林氏をリーダーとした巻機山北面の下ノ滝沢の山行であった。今にして思えば、会に入り立ての沢登りの「さ」の字も知らない新人をよく連れて行ったものだと感心させられる。それが、若林氏、そして、当時の『わらじの仲間』の懐の大きさの現れだったのだろう。その後の山行や会活動においても、ありがちな入会年度による上下関係、それによる待遇の差など全くなかった。むしろ、技術のある力のある先輩が一番幸い思いを自ら進んで引き受け、新人の体力面のみならず精神的な部分までサポートしてくれるという、(常識では当然なのだが)今までの環境では考えられない雰囲気であった。
今にして思えば新人をいつも連れ回してくれ、やる気さえあれば必然的にどんどん力がついていった。当然その分訓練的な山行も多く、ひと月の会山行が2、3回あることも少なくなかった。先輩であればあるほどより多くの訓練山行を含めた山行に参加していたし、より中心となって積極的に訓練を行っていたのも力のあるメンバーであった。
今年(2003年)の春、里の桜の花が今が盛りと燃える4月6日、「より困難な沢登り」を目指して入会し、「早く自立したリーダーとして山行をしたい」といつも真剣に山に向かっていた幹ちやん、そして、「より自分らしい山をやれる会を求めて」入会したばかりの坂本さんを山で失った。僅かばかりの生存の可能性を求めて深夜の北俣谷の捜索、雪崩に巻き込まれたことが原因の遭難であるが故に、頭の中ではほとんど「死」を覚悟していた。しかし、「魂」が、かすかな望みである「生存」の可能性を求めて身体を動かしていたし、幹ちやんと坂本さんを山で失った悔しさ無念さを噛みしめてもいた。それは、遺体が収容されたあの日、悔しいはど晴れ渡り遭難地点が見渡すことが出来る信濃大町に集まった会員、そして、都合でその場に立ち会えなかった会員の多くの想いであろう。
恐らく少なからぬ人数の会員が未だに気持ちの整理がつかぬままいるとは思うが、事故後のちょうど半年後にあたる2003年10月5日に、越後の小穂ロノ頭で会員だけでひっそりと追悼山行が行われた。当日は、前日から朝までの霙や雹混じりの悪天候からは想像もつかぬほどの青空が広がり、久しぶりに彼らと正面向き合うことができたことで、少しではあるが気分的に救われることができた。
『わらじの仲間』は、彼らにとって何であったのであろうか?『わらじ』は彼らに何を受け取ってもらえたのだろうか?
彼らにとって『わらじの仲間』にいたことが、薄っペらい言い方だが「幸せ」だったのだろうか?
私は、会の先輩として彼らから与えられたものにどれほど恩返しが出来たのだろうか? 会のチーフリーダーとして、そして、山の仲間として。
この年報が開かれるとき、また新たなるわらじ年度が始まっている。新しい風の中でもう二度と悲しく空しい気持ちを味わうことのないように、山、そして渓を楽しんでもらいたい。先輩達が築いたわらじの巨像から抜けだし、地に足が着いた『わらじの仲間』を育てることが、今のわらじにとって一番大切なことであり、今も野山を駆け巡っているであろうふたつの魂に対しての、せめてもの餞になるであろう。
そうでなければ、わらじの存在も意味がないものとなるだろうし…。
2003年 秋